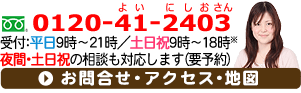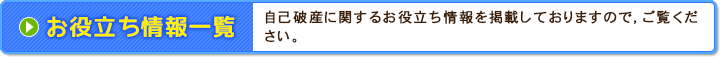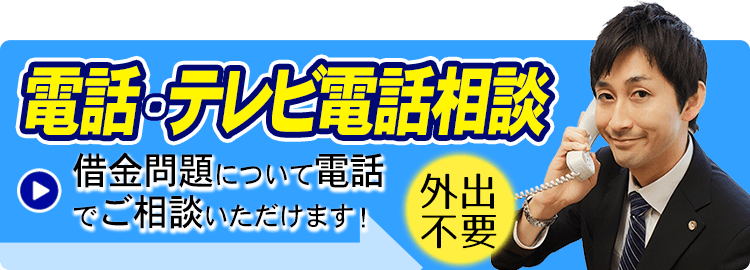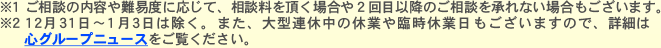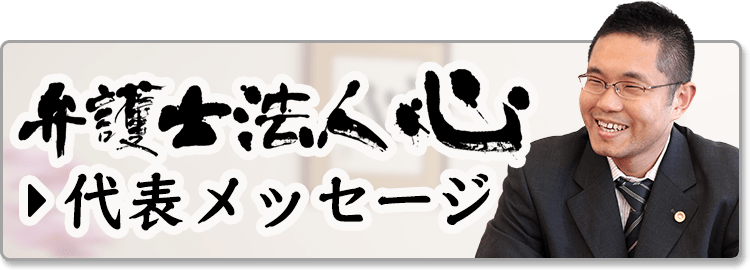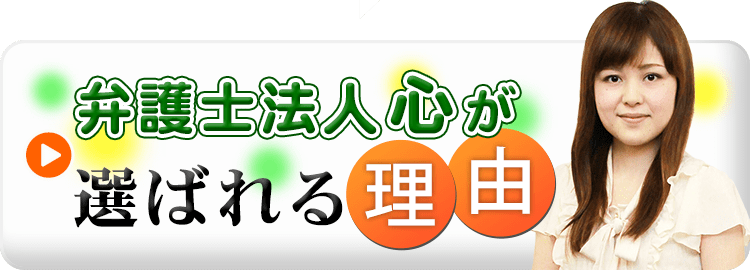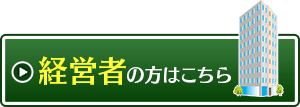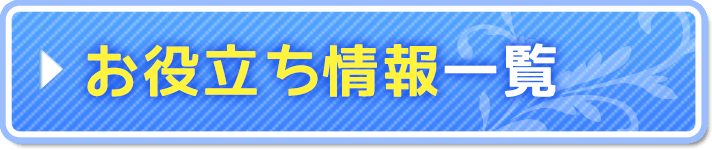Q&A
自己破産をした場合、配偶者にはどのような影響がありますか?
1 自己破産で発生しうる配偶者への影響は3つあります
自己破産は債務者個人単位で行われる手続きですので、原則としては配偶者の方への影響は発生しません。
ただし、次の3つのケースにおいては、法律上または事実上、配偶者の方へ影響が及ぶことがあります。
①債務者の方の家計に関する情報提供が必要なケース
②債務者の方の連帯保証人になっているケース
③債務者の方と共有している財産があるケース
以下、それぞれについて詳しく説明します。
2 債務者の方の家計に関する情報提供が必要なケース
自己破産を申立てる際に必要な資料のひとつに、申立て前数か月分の家計表があります。
また、収支を裏付ける資料が必要となることもあります。
配偶者の方が家計管理をしている場合には、家計表の作成にご協力いただく必要があります。
配偶者の方にも収入がある場合には給与明細の写し、配偶者の方の銀行口座から公共料金を引き落としている場合には、預貯金通帳の写しの提供を求められることもあります。
3 債務者の方の連帯保証人になっているケース
連帯保証人がついている債務を抱えた状態で自己破産をすると、連帯保証人に対し、その債務の残債額が一括で請求されます。
配偶者の方が連帯保証人になっている場合には、配偶者の方に一括請求がなされます。
配偶者の方において連帯保証債務の支払いができないという場合には、配偶者の方も債務整理を行うことになります。
なお、自己破産はすべての債権者を対象としなければならない手続きですので、連帯保証人がついている債務を除外するということはできません。
4 債務者の方と共有している財産があるケース
問題になりやすいケースとして、ご自宅を配偶者の方と共有している場合が挙げられます。
自己破産をすると、破産管財人が債務者の方の財産を売却します。
配偶者の方と共有している財産の場合、債務者の方の共有持分が売却の対象となります。
実務上は、債務者の方の共有持分を配偶者の方に買い取ってもらうか、配偶者の方の共有持分と一緒に第三者へ売却することをまず検討することが多いです。
美容ローンを組んでいるのですが自己破産できますか? Q&Aトップへ戻る